飛騨高山にやすらぎとひろがりを HOME
東やすひろは何をしてきた人なのか(JESCO)
今更ですが、有権者の方から
「東さんは何をしてきた人か。
経歴を見てもわからない」
と言われてしまいました。
新聞各社には
職務経歴書をお渡ししたのですが、
極々かいつまんだ記事しか出てない
と思います。
本当に今更ですが、少し紹介します。
まず、JESCO。
■JESCOについて
https://www.jesconet.co.jp/index.html より引用、抜粋
名称: 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
根拠法: 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
目的:
中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、中間貯蔵に係る事業を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理その他環境の保全に資するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業並びに環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供に係る事業を行うことを目的とする
資本金: 32,639百万円(全額政府出資)(令和4年2月末現在)
監督官庁: 環境省
■JESCOでの私の役割・仕事
【所属】
中間貯蔵事業部 技術課(本社 東京都港区芝)
【業務内容】
公募実証事業(除去土壌等の減容等技術実証事業)における
・事業者選定業務(予備審査、有識者委員への提言、ファンディング)
・採択事業の推進業務(仕様作成、事業者の業務計画作成の支援、進捗管理・試験立ち会い・指示、報告書作成指導等)
【ポイント】
環境省に代わっての実証事業の採択・推進。放射能を含む除去土壌等の減容技術のみならず、ドローン等ICT技術、理解醸成・リスクコミニュケーション等、幅広い科学技術(社会科学、自然科学)への理解力を発揮し、これまで担当した4案件で事業者を監督・支援し、事業を完遂させた。
要は、除去土壌等の再生利用・最終処分のための技術について
実証事業への採択に関わり、実証のために採択事業者がちゃんと試験等を行ったか、報告書はちゃんとしているか、技術的に監督・支援した、ということです。
【所属】
中間貯蔵事業部 技術課(本社 東京都港区芝)
兼 中間貯蔵管理センター 研究業務等推進課(福島県いわき市)
【業務内容】
除去土壌等輸送車両の入退域認証にかかるETCゲート管理システムの整備及び運用プロジェクト(委託業務)の発注者側主担当
【ポイント】
上記4億円超プロジェクトの主担当として、仕様作成、起案・幹部説明、環境省との折衝・契約変更、現場立ち合い(福島県双葉町・大熊町)、及び納品・検査に対応。会計検査院の検査にも応対。ETCゲートやETC2.0等交通系ICTへの理解力は勿論、輸送計画等にかかる環境省担当官との忍耐強い折衝力と正確かつ迅速な事務処理能力を発揮し、足掛け5年にわたるプロジェクトを無事完了させた。
要は、何百台もの土を運ぶダンプが中間貯蔵エリアに入るためのETCゲート(4カ所)や監視システムを、発注者として、設計・整備・運用管理した。
もっといえば、仕様書を書いて、指示書を出して、ちゃんと運用してもらうように監督した、ということです。
上記2つが大きなお仕事でしたが、
他にも、中間貯蔵施設地図情報システム(GIS)について、オープンソース(QGIS)ベースへの切り替え、その後の運用も担当しました。
すべての人が社会参加できるための取り組み
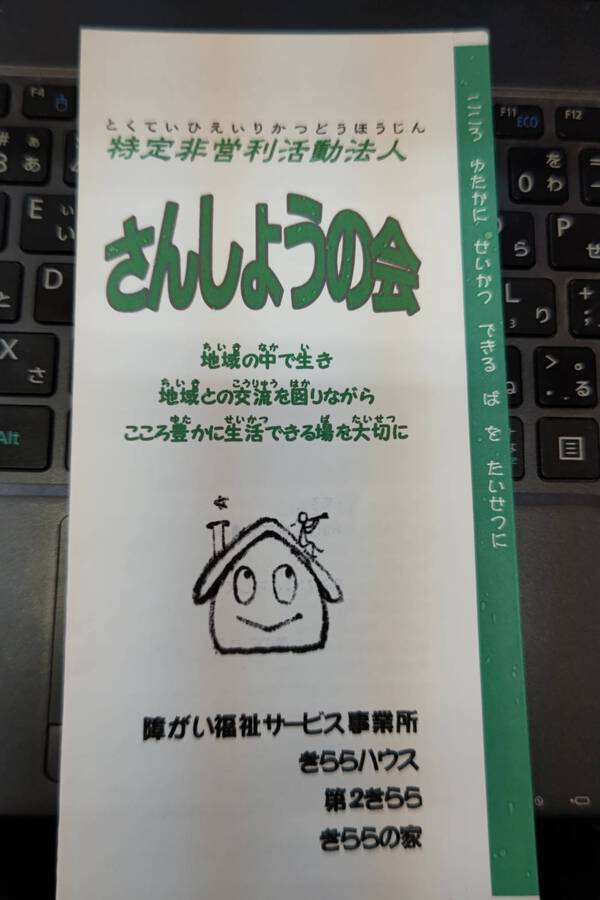
選挙公約の中に、
すべての人が社会参加できるための取り組みを進める
旨を記した。
当然、すべての人の中には
障がい者が含まれる。
障がい福祉の実際について、
さんしょうの会元理事長の志賀さんにお会いして
きららハウスでのとりくみである
就労継続支援、生活介護の実際について
リーフレットも交え、お話をいただいた。
リーフレットには、
・作業や創作活動を通して、
物を作る喜びや達成感を感じ、
地域とつながることができる場を提供します。
・仲間(利用者)の人格や思いを尊重し、
どのように生活するか、
どのように生きるかを
自分で選び、決め、
その実現に向けて支援します。
とある。
言葉で書くのは易しいが、
これを30年以上、実践されてこられたのだ。
時間と私財をなげうってまで取り組んでこられたのだ。
すさまじいことだ。
私の妹も障がい者(聴覚障害者)であった。
母が、月曜日の早朝、まだ幼い妹を、
汽車(高山6時42分発のりくら2号か、その前の始発の普通列車)で、
岐阜市加納の聾学校に連れて行き、
金曜日に連れて帰る。
そんな母と妹の姿を、
父と一緒に、見送り、出迎える。
子どもの頃、そういう生活が続いた。
そんな話を志賀さんと交わしていて、
自分は、泣いていた。
涙が止まらなくなっていた。
障がいを持つ方に、
社会参加の場を提供する。居場所をつくる。
自分らしく生きるための支援をする。
素晴らしい方が高山には居られる。
でも、
これまで、楽しんで、
そういうとりくみをしてきた、
仲間づくりをしてきた、
と、笑顔でおっしゃる志賀さん。
優しい笑顔の中に、強さを見た。
すべての人が社会参加できる取り組みを進める。
言葉で書くのは易しいが、実践するには覚悟が要る。
高山にやすらぎをつくる。やらなだしかん。
先輩に学ぶ:大江元村長へのご挨拶

一之宮での活動。
ここには是非ともご挨拶したい方がおられる。
旧宮村 大江元村長。
お歳を伺えば驚くが、
高身長もあって、堂々とした佇まい、風格。
それでいて、優しい語り口。
まさにジェントルマン。
大江元村長のあまたの功績。
中でも、宮川の治水。ダム建設。
旧高山市街に住まわれている市民の方々は
大江元村長に感謝しなければならない。
日々やすらかに暮せるのは当たり前のことじゃない。
大江元村長と私の共通項。
大江さんも、外から、自分の故郷を見ていた。
県の立場からみて、故郷でなすべきことを考えた。
私は、東京から見て、故郷でなすべきことに気づいた。
大江元村長は、それを実行に移した。
私がまだ及ぶところではない。
でも、頂いた言葉の中から、私にも、
進取の気風がビシビシ伝わってきた。
愛すべき故郷高山。
でも、変わらなければいけない。
大江元村長は、
桜のまち一之宮づくりにも尽力された。
私も、希望の花を咲かせたい。
市民の皆さんを明るい気持ちにすること。
やらなだしかん。
学びについて思う

昨日は、スーパーのさとうさんの駐車場の一角をお借りして
街頭演説をさせて頂きました。
他にも、多くの場所をお貸し頂きました。
誠に有り難うございました。
うち1つは、まさに私の通った山王小学校の近く。
調子に乗って、山王小校歌を歌いました。
♪ 流れは尽きぬ宮川の
恵み豊かな高山市
日枝の杜の空晴れて
甍煌めく学び舎は
我らが山王小学校 ♪
私の記憶のままです。
漢字表記については、違っていたら、ごめんなさい。
思えば、担任の先生には大変お世話になりました。
1,2年 国府の大池敦子先生
3,4年 糸田ひさ子先生(故人)
5,6年 大新町の糠塚良一先生(ぬかせん)
多感な5,6年生のときのぬかせんの授業は
およそ、学校指導要領には則っていないもので(失礼)、
そのときの社会の話題とか、科学の話題とか、
あれやこれやを先生が話し、
生徒に質問し、答えさせたりするものでした。
いんち(岩本伸一君)も、さわこ(沢田浩一君)も
同じ空間にいました。
あのときの先生とのやりとりが
今の自分に繋がっているのだと思います。
子どもの頃に受けた教育は、
その後の人生に大きな影響を与えるものです。
でも、人はいつも学ぶことができます。
好奇心があれば、向上心があれば。
学校で勉強しなかったことを後悔している人もいるかもしれません。
だったら、今から学べばいいんです。
私は、政策として
すべての世代に学びの機会を提供する
ICTを活用して、どこに居ても何歳からでも学べる環境をつくる
と掲げさせて頂きました。
インターネット上には、
たくさんのコンテンツがあります。
サービスがあります。
東京通信大学のようなインターネット大学もあります。
私自身も、京都大学の博士号を取得したのは、
2016年 52歳の時です。
それまで国外の学会誌に投稿した論文を
教授の指導の下、日本語にまとめ直すのは大変でしたが、
50歳を過ぎて、学びがあり、楽しい時間を過ごせました。
いつからでも、高山にいても、学ぶことはできます。
好奇心のある方、向上心のある方は、チャレンジしましょう。
チャレンジしなかったことで後悔するような人生から脱却しましょう。
私も、今、チャレンジしています。
明日(25日)も頑張ります!
コロナ感染者の状況にかんがみて
屋内での個人演説会については、
私、東やすひろの判断で、
現在、見合わせております。
お暑い中、申し訳ありませんが、
皆さん、屋外でお会いしましょう!
NTTに就職した理由

私がNTTに就職したのは、平成2年のことです。
大学で分析化学の研究をしていたことから、
それを活かせる就職先を探しました。
当時、修士課程の大学院生。25歳。
最終的に2社に絞りました。
1社は〇〇重工。日本を代表する企業です。
大変熱心に誘ってくれました。
ただし、想定される就職先は関西の分析研究室。
迷いました。
もう1社がNTT。
半導体の作製、評価・分析を行っていた研究所への配属を望んでました。
が、その一方で、思うことがありました。
研究業務が一段階ついたら、
岐阜県内か、名古屋あたりに転勤させてもらおう。
NTTだったら全国津々浦々にある。
両親にも、そのように説明して、NTTに入りました。
しかし、NTTはその後、分割され、
最初にNTT移動通信網(現NTTドコモ)が分かれ、
その後、NTT持ち株会社と
NTT東日本、NTT西日本となりました。
私はNTT持ち株会社研究所所属となりました。
NTT東日本、NTT西日本は、更に、
いわゆるハイフン会社にまで分離分割されました。
当時、日本の人口問題は、
「超高齢化社会」という言葉で語られていました。
現在のような少子化というイシューが全国的に叫ばれだしたのは
日本の人口がピークを迎え、以降減少に転じた
平成20年前後以降でしょう。
高山市について言えば、全国より早い
平成12年をピークとして、減少に転じています。
私が東京に就職した平成2年はバブル期でもあり、
その後の日本の凋落、
ましてや、少子化については
まだ社会的な問題として多く語られていなかった頃です。
翻って今、
結婚観はじめ、多様な考え方がある中、
少子化の問題は、行政のみならず、
皆で考えなければならない問題です。
私も、市民のひとりとして、
高山市の少子化について考えさせて頂きたい
と思います。
2人の子どもを共に育てた妻の意見も参考にします(笑)
デジタル「山の都」構想実現への要諦

政策として、デジタル「山の都」構想を掲げています。
高山は日本一広い市であり、
「山の都」という言葉どおり、山間部がほとんどであり、
支所部の生活を含む今後の市民生活を支える上で、
ICT活用・デジタル化はなくてはならないものとなります。
身近なところでは、
実際、今日、清見のななもりでも
スマホ教室の案内をされているドコモの方にお会いしました。
さて、デジタル「山の都」構想について、私は、
・「行かんでも用事が済む市役所」ということで、
高山のどこにいても
デジタル活用で暮らしの便利や快適が享受できる
・近い将来、支所部の集落に、
ドローンでお薬やワクチンを届ける
といった未来像について語りました。
ただし、これは分かりやすい未来の結果の例です。
もっと大事だと思っているのは、実現に向けた過程。
デジタル「山の都」構想実現への要諦は、
市役所デジタル化の推進にあります。
何故か。
デジタル「山の都」構想を市が掲げた途端、
それは市職員にとって新しい業務となります。
しかし、コロナ禍があって、
行政の仕事は既に膨大になっており、
市職員の方々は疲弊しています。
人的リソースに限りがある中、現状のまま、
新しい業務を追加することには無理があります。
新しい業務は、必然的に、不定型業務になります。
市役所デジタル化で、
まず、定型業務をデジタル化する。
次いで、その分、不定型業務に職員が関われる時間を増やす。
この順序でないといけません。
デジタル化の中心となる人材については、
専門性を持つ外部人材を全国から公募し登用する。
その上で、デジタル化を実施できる市職員の育成を進める。
市職員の皆さんに向けて、
「ただ、デジタル化をやれ!」では、
市役所デジタル化は進みません。
さらに疲弊させてしまいます。
デジタル「山の都」構想への実現に向けて
私は、具体的なステップを踏んで進める考えを持っています。


